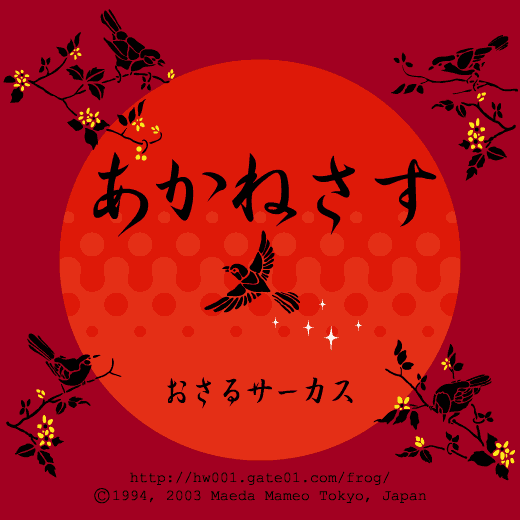
|
紅 (べに・くれない) ca002e C10・M100・Y60・B10 | 紅花の花弁の色素から染め出されるあざやかな赤。 紅花はエチオピアからエジプトあたりが原産地と考えられ、 シルクロードを通じて、紀元前二〇〇〜三〇〇年頃に中国の西方にもたらされたといわれる。 日本に紅花が渡来したのは五世紀頃で「呉」(くれ・揚子江の南)からきた「藍」(当時の日本における染料の総称)という意味で 呉藍(くれあい)と呼ばれ、それが「くれない」へと変化したと考えられる。 また「紅」は、中国渡来の紅という意味で「唐紅」「韓紅」(からくれない)とも呼ばれた。 紅花は貴重な染料であったため、濃染(こぞめ)は禁制(禁色)となった。 しかし、京の都の上流階級を中心に、大変な出費を惜しまず紅染を手に入れようとする人が後を絶たず、 当時より紅の色がいかに日本人を魅了していたかがうかがわれる。 同じ紅花で染めた色に、「褪めた紅」という意味の[褪紅](たいこう・あらぞめ / C13・M58・Y36・B0)と、 紅の濃度の薄い[薄紅](うすくれない / C0・M60・Y38・B26)がある。 |
|
緋 (ひ・あけ) de1908 C13・M90・Y95・B0 | アカネで染めたもっとも鮮やかで、黄みを感じさせる赤。 アカネは温帯アジア原産の植物で、古代にはすでにインドからペルシャ、エジプトにまで分布が拡がっていたという。 「あけ」は、日や火の色を表す「あか」と同意語である。 中世の軍記物には、源平の合戦において、勇敢な武将が、緋色に染めた糸でつづった緋縅の鎧、 あるいは緋色の直垂や袴を身に着けて奮戦するさまが記されている。 敵・味方に自らの活躍を印象づけ、武勇を誇示したい武将にとって、鮮やかな明るい緋色の赤はうってつけの色だったともいえる。 この[緋]には、暗い黄みの赤である[深緋](ふかひ・こきあけ / C20・M95・Y90・B57)と、 浅く染めた緋色の[浅緋](あさひ・うすあけ / C0・M82・Y54・B18)のバリエーションがある。 [深緋]は、文武天皇の大宝元年(七〇一年)の服制で赤紫に続いて位階が高く、その次に続くのが[浅緋]であった。 |
|
猩々緋 (しょうじょうひ) f41705 C4・M91・Y97・B0 | 黄みの強い冴えた赤。 ケルメス、あるいはコチニールという虫から抽出した染料などで染められた。 「猩々」は、猿に似た伝説上の動物で、その血はもっとも赤いとされた。 中国では「猩々」という語を、色が非常に赤いことのたとえに用いた。 また、濃い紅色を「猩々」、赤い着物を「猩袍」といい、猩々の血のように鮮やかな紅色を「猩紅」と呼んだ。 「猩々緋」は、「紅」を「緋」に換えた日本名であると考えられる。 「猩々の血で染めた赤」を意味するこの緋色は、魔除けの呪力を持つと信じられ、 とくに、猩々緋の陣羽織は戦国武将の間で愛用されたという。 |
|
朱 (しゅ) fd2816 C0・M85・Y85・B0 | 鉱物性顔料の朱によって染められた黄みの赤。 朱は水銀の硫化物で、天然の硫化水銀の原鉱は朱砂、真朱といわれた。 とくに中国辰州産の良質な朱砂が有名だったことから「辰砂」という名でも知られた。 長安の都を手本にした奈良時代の平城京は、中国風に朱色に塗られた宮殿、官庁、寺社が造営され、 都を南北に横断する大通りは朱雀大路と呼ばれ、南の城門として朱雀門がつくられた。 また、室町幕府から安土桃山時代を経て徳川幕府の時代に至るまで、武将は公文書に朱色の印を押して権威の保証とした。 豊臣秀吉、徳川家康の頃は、朱印状をもつ者だけが海外渡航を許され、中国や南洋との貿易に従事できた。 そういた権威を象徴する色としての朱色のイメージは、現代にも受け継がれている。 [朱]にはまた、水銀を焼いて作る赤色の人口顔料による[銀朱](ぎんしゅ / C2・M80・Y58・B20)と、 朱色の布を洗って退色させたような赤橙色の[洗朱](あらいしゅ / C0・M70・Y68・B10)がある。 |
|
丹 (に・たん) e62f16 C0・M80・Y84・B10 | 赤土の顔料や、黄土を焼いて赤くした顔料による赤。 鉛に硫黄と硝石を加えて焼いた酸化鉛による「鉛丹」も含まれる。 古代より丹は、錆止めとして舟や建物、器の塗装に使われていた。 これは、中国や朝鮮半島から日本に渡来した技術のひとつと考えられる。 神社の社殿や鳥居が赤く塗られた当初は、赤土の赭土による顔料を用い、やがてそれに鉛丹を加えた丹塗になったといわれている。 こうしたことから、丹色は、呪術的な意味や神秘的な力を象徴する色として捉えられていった。 また、「鉛丹」の色に似ている染織の色である[黄丹](おうに / C0・M70・Y70・B0)は、紅花とクチナシによって染めた色。 元正天皇の養老二年(七一八年)、皇太子礼服として黄丹衣(おうにのきぬ)が定められた。 これは、黄丹を曙の太陽の色に見立て、やがて天位につく皇太子の地位を象徴したからである。 以来、この色は禁色となり、皇太子の正式の礼服の色として現在まで続いている。 |
|
茜 (あかね) a20021 C0・M100・Y60・B35 | アカネ(茜)の根から採った染料で染めた濃い赤。 アカネの染料は媒染剤の種類や量によって色が変わる。 また、ムラサキグサと混ぜて染められることもあり、紫ぎみの赤から、黄みの強い赤まで、アカネが関わる色の幅はかなり広かったと考えられる。 そうした茜色のイメージから、「あかねさす」は「日」「昼」「照る」「紫」などにかかる枕詞として用いられた。 |
|
代赭色 (たいしゃいろ) bd3d1d C26・M74・Y83・B0 | 赭といわれる赤土の顔料による黄みの赤。 古く中国では、代州(山西省)に良質の赭が産出し、「代州赭」と呼ばれて広く愛用され、次第にこの名が赭の顔料の一般名となった。 「代赭」はその略称である。 |
|
弁柄色 (べんがらいろ) 7d1d14 C18・M80・Y79・B40 | 鉄分の多い土を焼いて作った顔料の中でも、赤い色は「弁柄色」と呼ばれた。 東インドで産出する酸化鉄粘土が、南蛮貿易で日本にもたらされ、顔料や製法が伝えられた。 「弁柄」は「ベンガル」の当て字といわれ、「紅殻」「紅柄」とも書かれる。 |
|
栗色 (くりいろ) 3d0d03 C20・M81・Y95・B70 | 栗の実の皮のような暗い黄みの赤。 「栗皮色」「栗皮茶」とも呼ばれる。 また、平安時代には「落栗色」ともいわれ、『源氏物語』にもその名が登場した。 |
|
葡萄色 (えびいろ) 430315 C34・M97・Y60・B60 | 蘇芳より暗い紫みの赤。 エビカズラ(葡萄葛)という山葡萄の一種の実が熟したような色という意味でこの名がついた。 『延喜式』では、葡萄色はムラサキグサを使って染める色とされ、赤みの強い赤紫を指していたと考えられる。 |
|
臙脂 (えんじ) 9c001f C34・M100・Y74・B7 | ラックムシやケルメス、コチニールなどの昆虫の分泌液によって染めた濃い赤色。 この染料はすべて日本では海外からの輸入であった。 南洋産のラックムシの分泌液を綿にしみ込ませて乾燥させたものが生臙脂で、これを再び水に溶かして染料や絵の具として使った。 |
|
牡丹色 (ぼたんいろ) ca2e94 C18・M82・Y0・B0 | 牡丹の花びらのような、濃い紫がかった紅色。 牡丹の花は、中国において観賞用として親しまれ、唐の時代には、則天武后が宮中に植えることを勧めたことから「富貴の花」と形容されるようになった。 日本へは奈良時代の終わりから平安時代のはじめにかけてもたらされ、唐と同じように愛好されたという。襲の色目にも「牡丹」という名がある。 |
|
東雲色 (しののめいろ) fb624a C0・M62・Y58・B0 | 明け方の東の空の色のような浅い黄赤色。 曙色(あけぼのいろ)ともいう。 近世に入ってから見られる色名である。 |
|
檜皮色 (ひわだいろ) 4d2321 C0・M57・Y42・B69 | 檜(ヒノキ)の樹皮のような色。 焦茶に近い暗い黄みの赤。 実際に檜皮を染料として染めた色のこととも考えられている。 古くは蘇芳の黒みがかった色をいった。 |
|
蘇芳 (すおう) 7b1e36 C52・M86・Y63・B0 | スオウ(蘇芳)というマメ科の樹皮などに含まれる色素によって染めた、濃い紫ぎみの赤。 一〇世紀に編纂された『延喜式』では、この色は紫に次いで、高貴な人に許された特権的な色であった。 襲の色目にも「蘇芳襲」があり、『枕草子』や『源氏物語』にも登場する。 |
|
小豆色 (あずきいろ) 632021 C0・M70・Y50・B60 | 小豆の実の色のような、にぶい赤紅色。 江戸時代から見られる色名で、近松門左衛門の作品などにも登場した。 着物の染織によう用いられ、赤小豆縞が、市松染や丹後かすり縞とともに流行したという。 |
|
珊瑚色 (さんごいろ) f86578 C0・M60・Y32・B0 | 黄みがかった薄い紅色。 英語でいうコーラル・ピンクにあたり、これも赤い珊瑚の色に由来する。 赤い珊瑚は古来より珍重され、日本では中国伝来の絵の具として用いられた。 |
|
撫子色 (なでしこいろ) f07896 C0・M50・Y16・B4 | 撫子(ナデシコ)の花のような色。 薄い赤紫。 当時、愛好された紅花で染められた薄い紅色で、平安時代には、襲の色目にも使われていた。 |
|
今様 (いまよう) bf2c4a C4・M79・Y40・B20 | 紅花で染めた薄い赤。 人気の高い紅花で染めた今流行りの色という意味で、平安時代に用いられた。 一説には、紅梅の濃い色ともいわれている。 |
|
桜色 (さくらいろ) fddbdd C0・M16・Y5・B0 | 桜の花のようなごく淡い赤。 やや紫みの薄い紅色。 平安時代より、花といえば桜をさすほど日本人に親しまれてきた花であり、美しい色として襲の色目にも用いられた。 |
|
紅梅 (こうばい) f07896 C3・M54・Y20・B0 | 撫子色よりやや明るい、鮮やかな薄い紅。 紅梅の花のような色。 春の到来を告げる色で、王朝文学の中では、紅梅色は美しい色の代表として登場する。 |
|
一斤染 (いっこんぞめ) fde4dd C0・M13・Y8・B0 | 紅花一斤で絹一疋を染めた色という意味。 紅染の淡い色。 紅は一般の人々に着用を許されない禁色であったが、紅に対する愛好はやまず、 一疋の絹を一斤の紅花で染めた色は許され、この淡い聴色(ゆるしいろ)が流行した。 |
|
躑躅色 (つつじいろ) ed1d75 C3・M90・Y16・B0 | 赤い躑躅(ツツジ)の花のような、鮮やかな紫がかった赤。 襲の色目にも躑躅襲がある。 牡丹色と同じように春に着る色とされた。 |
|
桃色 (ももいろ) f86578 C0・M62・Y31・B0 | 桃の花のような薄い鮮やかな赤。 西洋のピンクと混同されることもあるが、ピンクはナデシコ科の花を総称する色で、桃色とは色の由来が異なる。 |
|
鴇色 (ときいろ) f981ab C0・M50・Y10・B0 | 国の特別天然記念物であるトキ(鴇)の風切羽のような薄い紫みの赤。 この色が愛好されたのは江戸時代になってからのことで、若い人の着物の色として人気が高かったという。 トキは、朱鷺、桃花鳥などの異名もある。 |
|

 日本の赤
日本の赤